大切な仕掛け
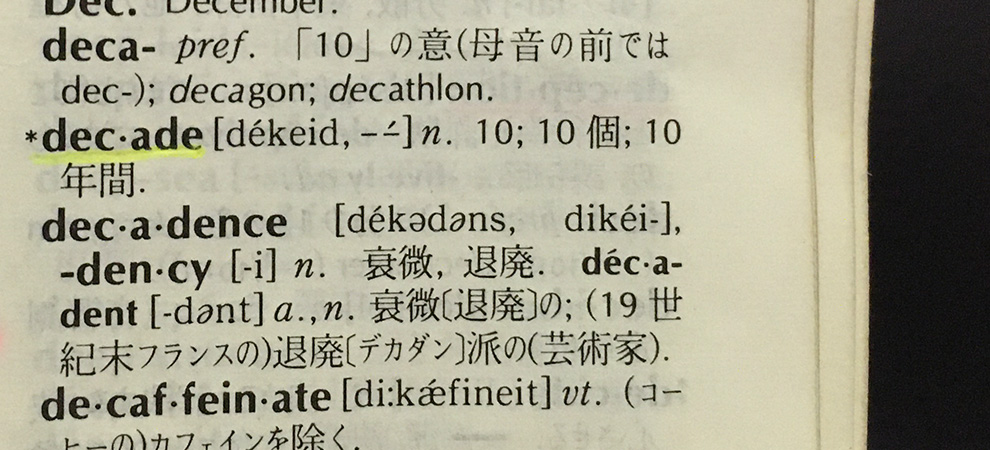
三省堂デイリーコンサイス英和辞典より(前回の投稿にも出てきた辞書です)
高校受験の勉強をしていた時なので、14、5歳の頃だったと思います。英単語帳に出てくる”decade”という単語の意味がわかりませんでした。正確には、意味がわからなかったのではなく、単語の存在意義そのものが理解できませんでした。「10年をひとくくりの単位とすることに何の意味があるのだろう。」単語を目にするたびに、そう思っていました。当時の自分から10年の時を引けば幼稚園児となってしまうわけで、当然と言えば当然の感想だったのだろうと思います。実体験からの感覚とはあまりにかけはなれた意味を持つこの文字列を、大人の都合で覚えなければならないことに対して、どこか腹立たしさすら感じていたことを記憶しています。
東日本大震災から10年ということで、最近、ネットやテレビでは、震災関連の様々な特集を目にします。10年前の3月11日、僕はまだイギリスから戻って2週間も経っていませんでした。自宅の家具の配置替えをしていたところに大きな地震がありました。経験したことのない揺れだったので、震源は東京のすぐ近くではないかと思いましたが、実際には東北沖だということをテレビの速報で知りました。全てのチャンネルが緊急報道へと切り替わり、しばらくすると名取川周辺のヘリコプターからの中継映像が映りました。そこでは黒い水が茶色い畑をどんどんと飲み込んでいました。道路を走る白い車も何台か見えました。その黒い波が津波だと理解するのに、少し時間がかかりました。大学時代、津波の研究をしていたのにも関わらずです。
僕は男三人兄弟の長男ですが、2011年当時、たまたま弟たちは、それぞれの理由で仙台に住んでいました。幸い、その日の夜にはふたりの無事を確認することができましたが、凄まじい被害が出ている中で、それが本当に幸運なことだったとわかり始めたのは、翌日以降、災害の詳しい情報が入ってくるようになってからでした。

高台からの南三陸町 2012年1月
震災の翌年、AAスクールと在英日本大使館の主催で、宮城大学の学生の方々の協力のもと、ロンドンと被災地の子供たちを結ぶ、”Yatai Here Yatai There“というワークショプが企画され、僕は日本側のAAチームの一員として被災地を訪れました。当時、建築に携わる人たちは皆、自然の圧倒的な破壊力に対し「建築とは一体何なんだろう。」と、自問を繰り返していたと思います。もちろん僕もそのひとりでしたが、目の前にした瓦礫の山からは、ただただ冷徹な現実が伝わってきました。あの湿った空気の匂いは今でもはっきりと覚えています。
数年前から、建築の設計にあたり、目の前の課題だけでなく、建築というジャンルそのものが何千年と抱え続けてきた命題と深く向き合いたいと考えるようになりました。ここには、震災をきっかけとした建築家としての自分自身への問いかけが、やはりどこかで影響していると思います。
改めてこの10年を振り返ると、本当に多くの出来事がありました。いろいろとありすぎて、やはり10年をひとつの塊として捉えることはできそうにもありません。結局大人になっても同じでした。ただ、今は”decade”という単語の存在意義は感じられるようになりました。10年という単位は、区切りでもなく、くくりでもなく、連続する毎日を次の一日へと着実に繋げるために、大人たちが自らに用意した大切な仕掛けなのだと思います。

南三陸町 ながしず荘にて 2o12年5月